|
【 三社祭礼囃子の由来 】
祭礼ばやしは、今からおよそ五百年前即ち室町時代に大成された能楽より起こったもので、享保の始め江戸葛西金指村の香取明神の禰宜能勢環という人が創案して若衆達に教えたのに始まり葛西囃子と名付けて江戸の大祭り即ち神田祭り山王祭りなどに招かれて囃したもので、これがいつか将軍の上覧祭りの囃子となって江戸を風靡しました。
当時横須賀城主西尾隠岐守忠尚(にしおおきのかみただなお)公の参勤交代の折りに、その御家人衆が競って習ったものが御家人囃子と名付けられました。忠尚公には病悩の童子があり御家人衆がその慰めのためにと江戸より齎らした囃子がいつしか城下の町方に広まり遂に三熊野神社の附け祭りに用いられたことが三社祭礼囃子の根元であります。
年を経て文政年間、囃子の調子の乱れたのを嘆いた町方の有志がはるばる江戸に赴いてならい直し、それに新手を加えて横須賀固有の調子をあしらい、更に明治の初年有志が再び江戸に出て技を練ったと伝えられるように芸能三社祭礼囃子を完成させるまでには古来郷土人の幾多の苦業が重ねられています。
三熊野神社の附け祭りは旧幕時代にはすべて奉行所の指示に従って行われ、囃子はお城の東追手門から打ち始められていました。
三社祭礼囃子の曲目は大間、屋台下、昇殿、鎌倉、四丁目、馬鹿囃子の六曲に分かれています。
囃子道具は大太鼓一、小太鼓二、摺金(四助)一、笛(とんび)二、の四種で、大太鼓は普通一尺五寸のもので、小太鼓は二挺掛、摺金は唐金五寸のものを用います。笛に大笛(一本調子の篠笛)を用いることは全国的に珍しいとされています。
手古舞踊りにはおかめと、ひょっとこがあって、おかめの踊りは昇殿・鎌倉・屋台下の曲に限り、女児によって踊られ、ひょっとこはそれ以外の曲目に行われる男の踊りとなっています。
大笛の名人として知られる人では、江戸角力の力士であった中野川荘八、明治に入っては石津に戸塚金作があり、太鼓では西新町に佐藤米吉、太田善吉郎などの故人の名が残っています。
三社祭礼囃子の名調子は世に比類のないもので古典郷土芸能として漸くその特色が認められ、昭和三十年静岡県無形文化財第一号に指定され保護を受けています。
【 三社祭礼囃子の曲目 】
役太鼓(儀礼太鼓)
・昇殿しょうでん~春富十一正伝という人の創始といわれる。承天楽の雅楽の影響もあり、正伝、昇天、聖天等の文字も用いる。「昇殿の曲」「鎌倉の曲」「四丁目の曲」は総称して「役太鼓」と呼び「儀礼太鼓」である。旧幕の頃は神前及び城主の前のみで行われていたのが、明治初年廃城以後、神前と横須賀地内十三カ町総代(祭典会所)前のみに改められ、行われている。昇殿の曲には「ひょっとこ」面で男児が両手に日の丸扇子を持って踊る。
・鎌倉かまくら~本源は鎌倉八幡の神楽の拍子に里神楽における風俗をあしらった曲。昇殿と供に祝儀囃子として用いる。「おかめ」面で女児が両手に日の丸扇子を持って踊る。
・四丁目しちょうめ~仕丁舞の語より曲名が起こる。「ひょっとこ」面で男児が両手に日の丸扇子を持って踊る。
道中囃子
・大間おおま~枹(ばち)の間合いを悠揚に打つので、この曲名が起こる。最も緩やかな調子の曲。祢里が道中を練り歩くときに行われ、この曲に合わせて手古舞と称する素朴で古風な踊りを「ひょっとこ」面で、男児が両手に日の丸扇子を持って踊る。
・屋台下やたした~祢里の初期のものは屋台風のものであったことが文献に見え、この曲の起こりは楽人が屋台の下で囃したことに始まる。調子はやや早めの曲。祢里が道中をやや急ぐときに行い、手古舞は「ひょっとこ」面を男児が両手に日の丸扇子を持って踊るか、又は「おかめ」の面で女児が扇と手拭いを持って踊る。
・馬鹿囃子ばかばやし~若囃子、若衆囃子、若者囃子、和歌囃子等より転訛した曲か。紀州和歌浦の漁夫が大漁のとき、舟板を叩いたことに始まるという。最も急調な曲。神社に祢里をねり込むとき、又は祢里と祢里との喧嘩のとき、及び千秋楽に行われたが、現在は千秋楽の囃子として行われている。この曲には、青少年が御幣や撞木を持って「般若」面で踊る。これらの踊りは全て豊年と平和を祈る踊りである。

ひょっとこ、おかめ、般若
【 囃子詞 】
囃子詞には「ヤレヤレ」「シタシタ」「シチャシチャ」「ソレ」「マァダ」「ズイト」「コリャ」「コーリャ」等あり囃子方と称する役係が多勢で囃子の間合いにかける。
「ヤレヤレ」「シタシタ」「シチャシチャ」等は大間の曲、屋台下の曲、馬鹿囃子の曲に用いる。
「ソレ」「マァダ」「ズイト」等は昇殿、鎌倉の曲に用い、「コリャ」「コーリャ」は四丁目の曲に用いる。因みに「シタシタ」の詞は城主が道を通過の際、「下に下に」の奴の掛声をもじったものと伝えられている。
【 使用する楽器の種類・数量 】
大太鼓一 (大撥宮太鼓で一尺五寸の高張りのもの)
小太鼓二 (締太鼓二又は三丁掛けのもの)
摺金一 (唐金五寸のもので四助とも呼ぶ)
篠笛一 (長さ約二尺の一本調子を用いることは全国的にも類を見ない)
拍子木一 (囃子の開始、終了の合図に用いる)
【 芸能を行う人の構成 】
大太鼓一名・小太鼓二名・摺金一名・笛吹者二名・拍子木一名・囃子方数十名・ひょっとこ面一名・おかめ面一名・はんにゃ面一名。
【 服装・持ち物等の名称・数量・現状 】
(1) 芸能を行う染め抜き揃いの絆天、腹掛、股引、三尺、手拭、白足袋跣足で藩政時代より江戸火消鳶風の勇み装束で、生粋の江戸風趣を伝えている。
(2) 持物の提灯は役割、及び年令段階により異なる。丸形提灯は総代及び組頭が持ち、ナツメ型提灯は大中老、中老、長提灯は若中老及び若衆等それぞれ各一個ずつ手にもつ。
(3) 面は手古舞の踊用に ひょっとこ おかめ はんにゃ 面の三種を用いる。
ひょっとこ面には、だるま、かえる、大笑い、塩吹等のそれぞれ異なるひょっとこ面を用い、おかめ面には天太、ウズメを用い、採りものは鈴や扇子などを持つ。はんにゃ面は御幣や撞木などを採りものとして持つ。
(4) 祢里ねりと称する横須賀固有の花車一がある。(山車ともいう)

大須賀町教育委員会作成パンフレットをもとに遠州横須賀三社祭禮囃子保存會さんの許可をいただき掲載させていただきました。写真はHP管理人撮影です。(2002/12/16)
《捕捉1》

三社祭礼囃子CD
1.役太鼓
2.大間
3.屋台下
4.馬鹿囃子
企画制作:遠州横須賀倶楽部、大須賀町観光協会
演奏監修:三社祭礼囃子保存会
《捕捉2》
→三社祭礼囃子の名称について
《捕捉3》
特一本調子の笛は主に遠州地方で使われており、大須賀町、大東町、浜岡町、磐田市、福田町、浅羽町、豊田町、春野町、森町、袋井市、掛川市などの祭礼囃子に用いられます。また「特一本調子」という言い方は正式ではありません。標準の一本調子よりも2寸(約6cm)も長いことから一本調子の更に上の特別版として呼ばれる俗称です。
左側:三社祭礼囃子の特一本調子
虎山作 長さ2尺(約60cm)
右側:標準的な一本調子
獅子田 長さ1尺8寸(約54cm)
所有:磐田市南島KHさん

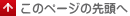
|




